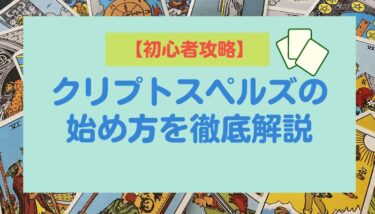「OpenSeaとRaribleの違いは?」「どっちがおすすめ?」などと気になっていませんか?
NFTの売買ができるOpenSeaとRaribleですが、特徴や料金の違いを知りたいという人も多いかと思います。
結論、OpenSeaとRaribleの大きな違いは「取引量」「ガス代」「独自通貨」です。
NFTマーケットプレイスを選ぶ際には、違いを明確化して選んでいくことが大切です。
本記事では、NFTマーケットプレイスのOpenSeaとRaribleの違いを、実際にNFTの売買をしている私が徹底比較していきます。
違いからわかるそれぞれのマーケットがおすすめな人もまとめているので、ぜひ参考にしてみてください。
OpenSea(オープンシー)とRarible(ラリブル)の比較

はじめに、OpenSea(オープンシー)とRarible(ラリブル)の概要や取り扱うNFTの種類、手数料などをまとめました。
OpenSeaの概要
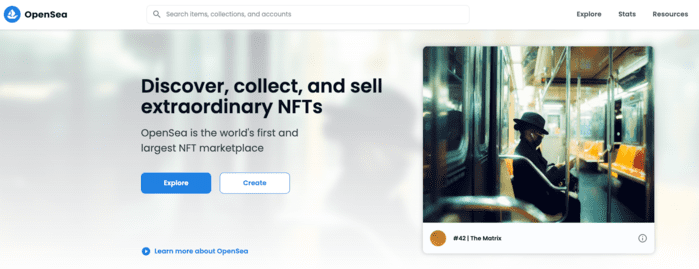 出典:OpenSea
出典:OpenSea
OpenSea(オープンシー)は、世界最大手のNFTマーケットプレイスとして有名です。
2017年12月にサービスを開始し、アート・ゲーム・音楽・デジタルファッション・デジタル不動産など扱うジャンルは多岐にわたり、世界中のNFTアーティスト・コレクターが登録をしています。
日本人クリエイターも多く出品しており、NFT初心者でも簡単に出品できる仕様となっているのも人気の理由です。
また、イーサリアムを利用する際に発生するガス代を抑えるために、「Polygon」「Klaytn
」「Solana」などイーサリアム以外のブロックチェーンも採用しています。
さらに、NFTの出品にはガス代と2.5%の販売手数料がかかるものの、2回目以降の出品はガス代が無料になるので「出品がしやすくなる」という特徴があります。
Raribleの概要
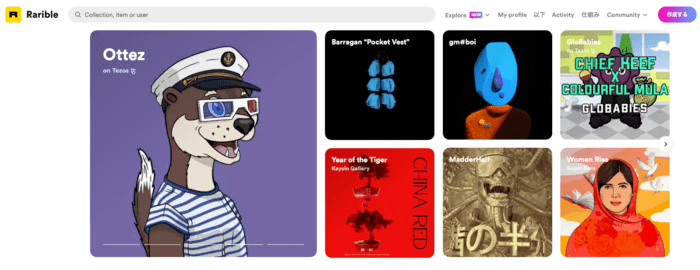 出典:Rarible
出典:Rarible
Rarible(ラリブル)とは、2019年からサービスを開始したデジタルアートを中心に取り扱っているNFTマーケットプレイスです。
ウォレットを接続してフォームを埋めるだけで簡単にNFTを作れ、無料でNFTを出品できます。
NFTの売買にはOpenSeaと同じくイーサリアムを利用しますが、他にも「Flow」「Tezos」「Polygon」など、イーサリアム以外のブロックチェーンも採用しています。
さらに、Raribleでは独自通貨「RARIトークン」を獲得でき、運営側と密な関係性を持つことが可能です。
【一覧表で比較】OpenSeaとRaribleの違い
次に、OpenSeaとRaribleの違いをわかりやすくするために、概要を一覧表にまとめてみました。
※表は横にスクロールできます
| OpenSeaの概要 | Raribleの概要 | |
| 取扱カテゴリー | ・デジタルアート ・イラスト ・ゲーム ・トレーディングカード ・音楽 ・写真 ・動画 ・デジタルファッション ・その他 | ・デジタルアート ・イラスト ・ゲーム ・トレーディングカード ・音楽 ・写真 |
| 決済可能な通貨 | ・イーサリアム ・Polygon ・Klaytn ・Solana | ・イーサリアム ・Tezos ・Flow ・Polygon |
| 利用者数 | 22万人 | 2万人 |
| 取引高 | 約700万ドル/日 | 約100万ドル/日 |
| NFT出品時にかかる 手数料 | ・販売手数料:2.5% ・ガス代(※2回目以降の出品時は無料) | ・販売手数料:2.5% |
| NFT購入時にかかる 手数料 | ガス代 | ガス代 |
| 対応ウォレット | ・MetaMask ・Torus ・Portis | ・MetaMask ・Torus ・Portis |
| 日本円対応 | × | × |
| 公式ページ | https://opensea.io | https://rarible.com/ |
※2022年4月時点
次の章では、上記の表からわかる「OpenSeaとRaribleの1番大きな違い」について解説していきます。
OpenSeaとRaribleの大きな違いとは?

OpenSeaとRaribleの1番大きな違いは、「取引量」「ガス代」「独自通貨」です。
ここでは、OpenSeaとRaribleそれぞれの特徴を確認していきましょう。
OpenSeaの特徴
OpenSeaの特徴は以下の通りです。
- オールジャンルのNFTを取り扱っている世界最大手のNFTマーケットプレイス
- NFT取引量が世界No.1
- 利用者数が22万人以上
- 他のマーケットに比べて高値でNFTが売買されている
- 2回目以降は出品時にガス代がかからない
OpenSeaの特徴は、やはり世界最大手のNFTマーケットプレイスという点でしょう。
利用者やNFT取引量が他のNFTマーケットプレイスに比べても圧倒的に多く、利用者数と取引高はともに世界No.1です。
世界中のクリエイターやコレクターが利用していることから、認知度を世界に広げていきたいと考えている人にはメリットが大きいと言えます。

「このNFTはどのマーケットで売れるのか?」と悩んだ場合、OpenSeaであればまず間違いなく販売をスタートできます。
さらに、OpenSeaでは他のマーケットに比べて高値でNFTが売買されているのも特徴の1つ。
初めてイーサリアムのNFTを出品する時にはガス代がかかるものの、2回目以降はガス代がかからないので収益化を目指せれます。
Raribleの特徴
対して、Raribleの特徴は以下の通りです。
- デジタルアートを多く取り扱っている
- 出品時にガス代を払わずともイーサリアムのNFTを発行できる
- RARIという独自通貨を発行していて、運営の一部に参加可能
- 販売されているNFTが全体的に安価
- 一部日本語に対応している
Raribleは2021年10月、「Lazy minting」という新機能を発表しました。
「Lazy minting」とは、クリエイターがNFTを出品するときに、出品者ではなく購入者側のみガス代を負担するように設定できる仕組みです。
OpenSeaでは2回目の出品からガス代がかからなくなりますが、Raribleは初回からイーサリアムを用意せずともNFTの発行ができます。

さらに、RaribleにてNFTを売買すれば独自通貨の「RARIトークン」を獲得できるのも特徴の1つ。
RARIはイーサリアムベースのトークンで、保有しておくことでRaribleの方向性を提案したり、方針の投票に参加することが可能です。
ちなみに、RARIトークンは毎週月曜日に販売者と購入者それぞれ50%ずつ分け与えられます。
株式のように運営側と接点を持ちつつ、別の資産を増やせるというのもRaribleならではの強みと言えるでしょう。
実際に使ってみてわかったOpenSeaがおすすめな人

違いを比較しつつ、実際に使ってみてわかったOpenSeaの利用がおすすめな人は以下の通りです。
- さまざまなジャンルのNFTを売買したい
- 積極的に売買が行われているマーケットでNFTの販売をスタートしたい
- NFTアーティストとして日本だけでなく世界にも認知してもらいたい
- 別のNFTマーケットで購入したNFTを転売したい
世界中のコレクターが注目しているマーケットでもあるので、日本だけでなく世界を視野に入れたアーティスト活動も可能です。
さらにOpenSeaは他のマーケットに比べて、高値でNFTが売買されていることも少なくありません。
そのため、NFT転売をしたい場合にもOpenSeaは最適と言えます。

実際に使ってみてわかったRaribleがおすすめな人

違いを比較しつつ、実際に使ってみてわかったRaribleの利用がおすすめな人は以下の通りです。
- デジタルアートのNFTをメインで売買したい
- 初回からガス代を払わずにイーサリアムのNFTを出品したい
- Raribleが独自で発行しているRARIトークンを獲得したい
Raribleは、特にデジタルアートをメインで売買するにはぴったりのマーケットと言えます。
また、初回からガス代を支払わなくていいので、気軽にNFTを出品したい場合にもおすすめです。
さらに、NFTの売買でRARIトークンが発生するという仕組みは、他のNFTマーケットにはありません。
そのため、マーケットの動向を楽しみながらNFTの売買をしたい場合に最適な場所と言えるでしょう。
まとめ

OpenSeaとRaribleの違いを徹底的に比較していきました。
それぞれの大きな違いは、「取引量」「ガス代」「独自通貨」です。
最後に、OpenSeaとRaribleの特徴とおすすめな人を一覧表にしてまとめます。
※表は横にスクロールできます
| OpenSea | Rarible | |
| 特徴 |
|
|
| おすすめな人 | ・さまざまなジャンルのNFTを売買したい ・積極的に売買が行われているマーケットでNFTの販売をスタートしたい ・NFTアーティストとして日本だけでなく世界にも認知してもらいたい ・別のNFTマーケットで購入したNFTを転売したい | ・デジタルアートのNFTをメインで売買したい ・初回からガス代を払わずにイーサリアムのNFTを出品したい ・Raribleが独自で発行しているRARIトークンを獲得したい |
NFTマーケットプレイスを選ぶ際には、マーケットの特徴を知りつつ、どんな目的でNFTを始めるのかを決めておくことが重要です。
本記事を参考に、ぜひ楽しいNFT生活を送ってください!







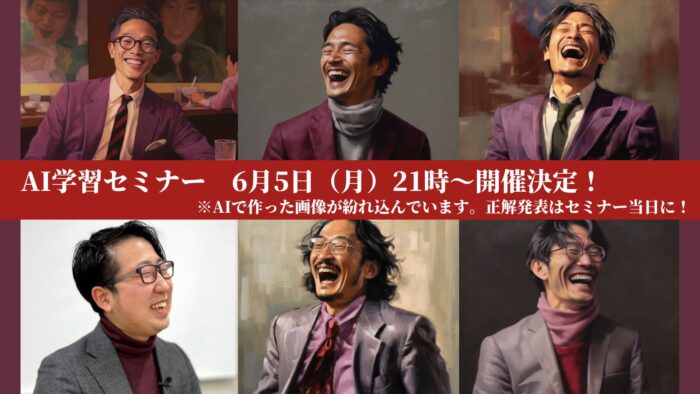


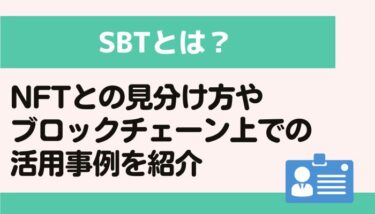
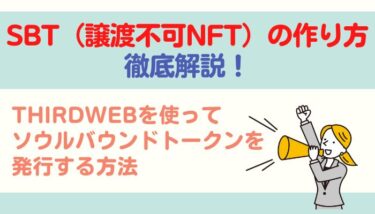
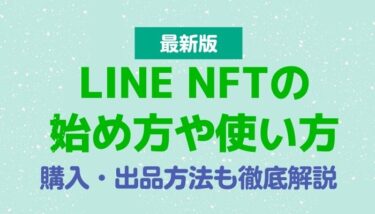

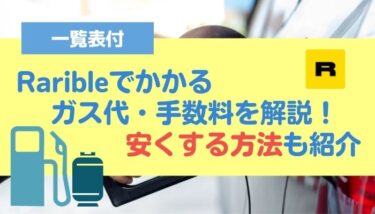
で-LANDを購入する方法-375x214.jpg)